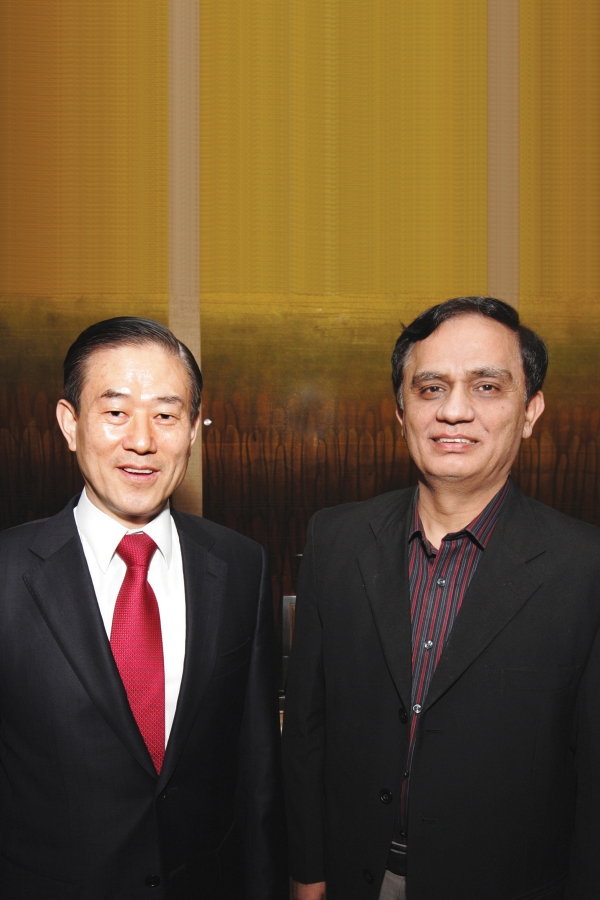
Ⅰ. 大きな喜びをもって主を賛美する救いの感激
詩篇126篇は「聖所へ上っていくときに歌う歌」の一つとしてよく知られている。イスラエルの民は毎日聖所に上り礼拝し、賛美をささげたが、その過程でしばしば詩篇126篇を歌ったという。特にバビロン捕囚から帰還したイスラエルの民の熱い感激と感謝がそのまま込められているこの詩は、彼らが受けた救いの喜びを生々しく表現している。「主がシオンの捕われ人を帰らせてくださったとき、私たちは夢を見ているかのようであった。そのとき、私たちの口には笑いが満ち、私たちの舌には賛美があふれた(1~2節)」という告白は、解放の瞬間を迎えたイスラエルの民が感じた想像を絶するほどの大きな喜びをよく示している。張ダビデ목師はこのみことばに注目し、「私たちも救われたときのその驚くべき感激をいつも覚えていなければならない」と強調する。
当時、イスラエルの民はバビロンで70年にわたる捕囚生活を送っていた。慣れない地で、かつてエルサレムの神殿で捧げた礼拝や自由な生活、そして何より契約の民としてのアイデンティティを失いつつあった。しかし、神の救いの御業が時至って成就したとき、彼らはまるで夢を見ているかのような歓喜を体験したのである。この詩はまさにその解放直後の信仰告白であり賛美であった。「主は私たちのために大いなることをしてくださった。私たちは喜んでいる(3節)」という告白から、バビロンの捕囚から解放してくださった神に対するイスラエルの民の賛美と感謝がどれほど熱かったかがうかがえる。
張ダビデ목師は、こうした背景から詩篇126篇を説き明かす際、歴史の中で神が成し遂げられた偉大な救いを、その民がどのように叫び賛美しているのか、その本質に深く迫る。その本質とはまさしく「神が私たちを救い出してくださった」という事実から湧き出る感謝と喜びである。イスラエルの民が歌った「夢を見るような」喜びは、罪と死の捕囚から解放されたすべての時代の聖徒にも同様に当てはまる。旧約時代のイスラエルが政治的・地理的な捕囚状態から解放された出来事は、新約時代の聖徒にとっては「罪の赦しと霊的救い」の真実へとつながるからである。イエス・キリストの十字架によって罪を赦された者は、まさに罪の捕囚生活から解放されたイスラエルの民のように、神に賛美と感謝をささげることができる。
実際、イザヤ書40章にも「あなたがたの神は仰せられる、『慰めよ、わたしの民を慰めよ...その労苦の時は終わり、その咎は赦されたのだ』(イザ40:1~2)」と預言されている。この預言は、バビロン捕囚生活が70年に達したとき、神が定められた時が満ちて解放を与えるという約束を含んでいる。そしてその預言は完全に成就し、バビロンに捕囚となっていた民がエルサレムに帰還した。こうしてイスラエルは「主は私たちのために大いなることをしてくださった。私たちは喜んでいる」と告白するに至ったのである。
張ダビデ목師は、この旧約の歴史的出来事がどのように新約の救いの思想へとつながるかを強調しながら、使徒行伝2章に描かれる初代教会の姿も同じ文脈で理解できると説く。使徒行伝2章47節の「神を賛美し、またすべての民に好意を持たれた。主は救われる人々を日々増し加えてくださった」という一節に見られるように、初代教会の中には「救われた喜び」があふれていた。回心し洗礼を受けた人々は日々神を賛美し、彼ら自身が喜びの礼拝共同体となったのだ。このように救いの喜びはすぐに賛美へとつながり、共同体の中で分かち合われるダイナミックな「いのちの力」を生み出す。
「主よ、ネゲブの流れのように私たちの捕われ人を帰らせてください(4節)」という節にある「ネゲブの流れ」とは、イスラエル南部のネゲブ砂漠を指している。乾季にはまさに何も育たない干からびた地だが、雨季になると水が流れて小川ができ、花が咲く。詩篇記者は神の救いを、このネゲブ砂漠に流れる小川にたとえた。すなわち、干からびた土地が水によって生き生きし、花が咲くように、神の救いが臨むと民の生活は一変するという意味である。この詩的表現は、バビロンから帰還したイスラエルの民だけに限定されず、私たち一人ひとりの人生にも適用できる。どれほど人生が乾き切り、苦しく思えても、神の救いが臨むと、干上がった地がいのちを回復するように驚くべき変化が始まるのだ。
張ダビデ목師は、これについて「教会共同体も同じである」と語る。どれほど教会が停滞していようとも、聖霊のリバイバルと御業によって活気を取り戻し、花を咲かせることができる。だからこそ、教会は時代を見極めてリバイバルを切望し、その火種を絶やさず世界宣教の礎として用いるべきだと強調する。救いの感激に満たされた人々が集まれば、自ずと賛美があふれ、その賛美はさらに宣教や救済、奉仕へと広がっていくからである。
実際、「涙を流して種を蒔く者は、喜びながら刈り取るだろう。泣きながら種を携えて出て行く者は、必ず喜びの束を携えて帰ってくるだろう(5~6節)」という節は、多くの聖徒に「種を蒔く」ことの意味を改めて考えさせる。ここでは、イスラエルの民が体験した「涙」と「喜び」が同時に強調されている。捕囚から帰還した後、土地を耕し種を蒔く作業は決して楽なことではなかった。荒れ果てた土地を切り開き、雨と太陽を待ち望みながら必死に農作業をする労苦が必要だった。しかし、涙をもって懸命に種を蒔く者に、神は必ず喜びの実りを与えてくださる。これがイスラエルの民の歴史において起こった具体的な出来事であると同時に、今日を生きる私たちに与えられた明確な約束でもある。
張ダビデ목師は、このみことばを人生のさまざまな領域に適用する。個人の霊的生活においても、家庭においても、社会や教会共同体においても、そして究極的には世界宣教の現場においても、この「種蒔き」の原理が必ず必要だというのである。農夫が畑に種を蒔くように、聖徒は伝道と宣教の現場に真理のことばを蒔き、愛と恵みを蒔き、分かち合いと献身を蒔かなければならない。その過程は苦しく痛みを伴うこともあるが、最終的には「喜びながら刈り取る」ことになるという聖書的約束を固く信じて進むべきだ、というメッセージなのである。
このように詩篇126篇は、捕囚生活からの解放、それによる救いの感激、そしてその感激を引き継ぐ賛美の重要性を際立たせている。この救いの賛美は、決して一度きりの感情の爆発ではない。共同体が日ごとに歌うべき継続的な宣言であり告白なのだ。初代教会共同体が「神を賛美し」(使徒行伝2:47)集まることを励んだように、今日の教会も救いの福音を胸に抱いて賛美すべきであり、その賛美は自ずと宣教への熱意へと結びつくべきだ、と張ダビデ牧師は力説する。
この賛美には私たちの「信仰告白」が込められており、特に罪の虜となっていた人間を解放された神の愛を証しするものである。また、詩篇記者が語る「ネゲブの流れのような解放」は、どれほど砂漠のように干からびた人生でも、神の恵みが臨めばまったく変わり得ることを示している。これこそが救われた聖徒たちの基盤であり力である。モーセが紅海の前で恐れる民を導き、神を賛美しながら行進したように、罪から解放された聖徒たちもまた、干上がっていた魂が小川の流れを受けたように新しい力を得て賛美するようになるのだ。
バビロン捕囚から帰還したイスラエルの民のように、現代を生きる私たちもさまざまな形で「捕囚状態」を体験する。人生の問題に縛られたり、病や経済的困難などで心が重くなることもある。しかし救いの福音によって罪から自由にされたならば、その解放感こそが「夢を見ているかのような」喜びを注いでくれる。そしてその喜びがあふれるとき、唇には自動的に賛美があふれてくる。これが詩篇記者の言う「私たちの口には笑いが満ち、私たちの舌には賛美があふれた」という表現の現代的適用であろう。
結局、詩篇126篇で私たちがまず確認すべき核心は、神の大いなる救いによって与えられる「喜びと賛美」の本質である。張ダビデ牧師はこのみことばを指して「救われた者に与えられる自然な実り」と語る。つまり、罪の赦しを体験した者が神の前に立つとき、「ただ恵みによる喜び」が心からあふれ出て、それが賛美として表れるのはごく当然のことだというのである。そして、このような賛美こそが苦難の中でも揺るがない希望の源となる。バビロン捕囚のように、長く続く停滞と痛みの時期を通る人々にとっても、神が救いの御手を差し伸べてくださるときに得られるあの歓喜は、まさにこの詩篇の記者が歌った感激と変わりない。
Ⅱ. 涙をもって種を蒔く者の宣教的使命
詩篇126篇5~6節にある「涙を流して種を蒔く者は、喜びながら刈り取るだろう...泣きながら種を蒔きに出て行く者は、必ず喜びの束を携えて帰ってくるだろう」というみことばは、現代教会の宣教・伝道の本質をよく表している。捕囚から帰還した民が荒れ果てた土地を耕しながら種を蒔いたように、今日の教会も「霊的な種」を世界に蒔かなければならないというのだ。張ダビデ牧師はこの節を指して、宣教がどれほど献身と犠牲を伴うものかを如実に示していると解釈する。
「涙を流して種を蒔く」姿は、決してロマンチックなものではない。実際の農夫が畑を耕し、種を蒔くとき、汗を流し、ときには失敗も経験しながら苦労して一年の農作を準備する。その過程には涙を誘うような環境や苦難がつきまとう。しかし聖書は、まさにこの汗と涙の労苦が無駄にならず、必ず「喜びの束」となって帰ってくると約束する。伝道や宣教も同様である。人々の無関心、拒絶、反対、あるいは迫害さえも受け入れなければならない時がある。それでも「蒔かなければ刈り取れず、蒔かれた種はいつか実を結ぶ」という聖書の法則は決して変わらない。
張ダビデ牧師は、新約聖書のマタイの福音書13章に出てくる「種を蒔く人のたとえ」と、使徒パウロが語った「宣べ伝える人がいなければ、どうして聞くことができようか(ローマ10:14)」というみことばを結びつけて説明する。福音の種を蒔く者は結果を保証されているわけではないが、神が働かれるとき、その種は成長し実を結ぶようになる。もちろん、石だらけの土地、茨の地、道端に落ちた種は実を結ばなかったり少なかったりする。しかし、良い地に落ちた種は30倍、60倍、100倍に実を結ぶ。宣教も同じだ。多くの人が福音を拒絶しても、いつか良い地のような心を持つ人々が御言を受け入れ、新生し、さらに福音を伝える者となって世界を変える可能性がある。
20世紀後半になると、宣教学界では「ミッシオ・デイ(Missio Dei)」というパラダイムが登場した。これは教会が「自己拡大」を目的に宣教するのではなく、神がすでに世を救うために働いておられるので、教会はその召しに参加すべきだという神学的視点である。かつては「教会中心の宣教」、すなわち「教会に来れば救われる」というような、やや閉鎖的で教権主義的な考え方が強かったが、新しいパラダイムは「神中心の宣教」へと転換された。まるで天動説(トレミー的世界観)から太陽中心の地動説(コペルニクス的世界観)に変わったように、教会中心の宣教から神中心の宣教へとパラダイムが変化したのだ。
張ダビデ牧師は、このような宣教的転換が詩篇126篇5~6節の「涙を流して種を蒔く者」の姿勢とも通じると説く。教会が自分の拡大だけを目的に種を蒔くのではなく、神がすでに用意された救いの御業に謙遜に参加する思いで献身するとき、初めて完全な実りを刈り取ることができるという意味である。グローバル化(Globalization)と情報化(Information technology)が進む現代は、インターネットや衛星通信の発達によって世界が「一つ屋根の下」にあるといっても過言ではない。スターリンク(Starlink)のようなプロジェクトを通じて、どこからでも制限なくネットに接続できる時代が開かれている。これは福音伝播において決定的な転換点になり得ると、張ダビデ牧師は指摘する。統制され閉ざされていた国々や、聖書所持が禁止されている地域でも、人工衛星通信を通じて福音に触れられる窓口が開かれるからだ。
では、教会はこの大きな技術発展の中でどのような姿勢をとるべきか。まさに「涙を流して種を蒔く者」としての決断である。この技術を単に世俗的な利益や趣味のためだけに使うのではなく、地球上のあらゆる地域に散らばる魂に福音を届ける道具として活用しなければならない。聖書はお金を「すべての悪の根」とし、神と並び仕えることはできないと教える(Ⅰテモテ6:10、マタイ6:24)。しかし宣教の目的、神の国の拡張という目的のために企業家がビジネスを運営するならば、その富はもはや神に敵対する偶像とはならない。むしろ教会共同体や世界宣教の大きな資源となり得るのである。
こうした文脈で、張ダビデ牧師は教会のアイデンティティを「集まる教会」(教会内部の礼拝・教育)と「散らされる教会」(世に出ていく宣教・伝道)の二つに分けて説明する。伝統的な教会は日曜礼拝など「集まり」に重点を置く傾向が強かった。しかし、教会の本質は「散らされる」ことを通して「世界へ行く」ことにある。なぜならイエス自身が「あなたがたは行って、あらゆる国の人々に福音を伝えなさい(マルコ16:15)」「地の果てにまでわたしの証人となる(使徒1:8)」と命じられたからである。「集まる教会」が教会成長の一つの軸だとすれば、「散らされる教会」はその成長の実りを世に分かち合うもう一つの軸となる。張ダビデ牧師はこれを「イン&アウト(In and Out)」とまとめて呼ぶ。一方では教会は教育と礼拝を通じて聖徒を養い、同時に世に派遣されて神の国を証ししなければならない。
この二つの軸が同時に作動するとき、詩篇126篇の約束のように、涙を流して種を蒔いた者が喜びの束を刈り取ることになる。また、教会は「宣教のアヴァンギャルド(Avant-Garde)」であり「ベースキャンプ(Base camp)」でもあると表現される。たとえば登山にたとえるならば、頂上に至るために必要な一時的拠点がベースキャンプである。登山隊はそこで訓練し、物資を補給し、健康状態をチェックする。教会も同じだ。世界の各地に福音を伝えるためには「中心基地」となり、人々が霊的・実際的な訓練を受けて力を補充し、そこから散らされていく必要がある。
20世紀中葉以降、世界の教会は第1次・第2次世界大戦による莫大な人的被害と精神的衝撃、そして社会全般に広がった実存主義思想に直面した。人々は「世界」や「歴史」という巨大な概念に目を向けるより、「自分」という個の存在や実存に意識を傾け始めた。しかしキリスト教の信仰は、本質的に個人の救いと同時に社会の救いを追い求める。個人が神のかたちに創造され、それぞれの魂が神の前に尊いと強調しながらも、その社会と世界に対する責任意識を持つ。これこそが「世俗化神学」の主張の一つであり、個人の罪の赦しだけでなく、世界と歴史の救いもまた神の関心事だというのである。
張ダビデ牧師は、まさにこの点に教会の宣教と使命があると力説する。教会が世から隔離され孤立するのではなく、教会の垣根の外に出て「涙を流して種を蒔く」宣教的実践が行われなければならない。そのためにも、教会は根本的に自らを「送り出す団体」と認識すべきだ。人々はしばしば「宣教団体」と聞くと、教会とは別の特定組織を思い浮かべがちである。しかし本来、教会こそが最も根源的な宣教団体なのである。教会がしっかり集まって礼拝と教育を受け、しっかり散らされて世に出ていくとき、そこで福音が伝えられ、神の国の価値が実現していく。
さらに教会は宣教ビジョンを具体化するために「OC(Olivet Center)」のようなベースキャンプを築き上げてきたと、張ダビデ牧師は言及する。OCは宣教および弟子訓練の中心地であり、霊的リフレッシュや教育、そして戦略的企画が同時に行われる場である。詩篇133篇の「兄弟が連れ立って共に住むことは、なんとすばらしく、なんと楽しいことであろう」というみことばを引用し、異なる背景を持つ者たちが集まって同じ心で祈り、訓練を受けるとき、神はそこで新しい御業を起こされると解釈する。そして、サレプタ(サルバテ)のやもめが持っていたすべてをささげてエリヤを支えたとき、彼女の油と粉は尽きなかったように、教会が持っている資源を惜しまず宣教のために捧げるなら、神はさらに豊かに満たしてくださると強調する。
これはパウロの「宣べ伝える者がいなければ、どうして聞くことができようか(ローマ10:14)」という言葉とも通じる。誰かが行き、誰かが宣べ伝えなければならない。教会がただ座っていて、誰かが来るのを待っているわけにはいかない。涙を流して種を蒔く者だけが喜びの束を刈り取るからである。ガラテヤ書5章にある「肉の行い」と「御霊の実」の対比もまた、私たちが何を蒔き、何を刈り取るべきかをはっきりと示している。肉の行いは姦淫や汚れ、偶像礼拝、ねたみ、争いなどとして現れ、御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、節制という美しい特質を持つ。教会が蒔くべき種は、この御霊の実を結ばせる福音の種なのである。
張ダビデ牧師は具体的に、伝道はまず「個人伝道」から始まると強調する。イエスが「あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい(マタイ22:39)」と仰せられたとき、最初に愛すべき相手は私たちの身近な、家族や友人、職場の仲間といった人々だ。伝道の簡単な実践方法の一つは「あなた、教会に通っていますか?」というシンプルな問いかけから始まるかもしれない。たとえ少しぎこちなくても、こうした些細な会話の試みの中で驚くべき実りがもたらされる可能性がある。相手に拒絶されたり、無礼な対応を受けたりすることもあるかもしれないが、農夫がすべての種を同じ場所だけに蒔かないように、私たちもさまざまな人に福音の種を届けなければならない。
また、「もうすでに教会に通っている」と答える人の中にも、福音を深く知らなかったり、聖霊体験を持たない人は多い。表面的にはクリスチャンであっても、内面では世の価値観をそのまま維持しているケースも少なくない。だからこそ教会は「さらに深い福音、内面的にキリスト者となる道」を提示しなければならない。救われ、聖霊に満たされて、真に罪と死から解放された生活を送れるように助ける必要がある。それは「聖霊を受けなければ、決して完全な信仰生活を続けることは難しい」という神学的真理ともつながる。
黙示録3章20節の「見よ、わたしは戸の外に立ってたたいている...」というみことばのように、誰でも心の戸を開くなら主が入ってこられる。そのとき聖霊が臨在すれば、その人は新しい被造物となり、福音のために献身する人生を歩むようになる。張ダビデ牧師は、詩篇126篇5~6節が語る「喜びの束を刈り取る」という実りが、まさにこの「変えられた魂」を通して具体化されると教える。個人が再生(新生)するだけで終わらず、宣教の使命を受け継いで他の人に福音を伝えていく、そうした好循環が起こるとき、一つの家庭、一つの共同体、一つの社会が変革される可能性があるのだ。
特に、家庭が福音化されることには非常に重要な意味がある。張ダビデ牧師はこれを「ファミリー・チャーチ(Family Church)」とも呼び、小さな教会こそが家庭である点を強調する。家庭が福音の中でまっすぐ建てられるなら、その子どもや子孫たちが神を畏れ敬いながら生きる可能性は格段に高くなる。これはやがて宣教の持続的な原動力となり、世代から世代へ福音が継承される美しい通路ともなる。農夫が長い時間をかけて丹精込めて種を蒔いた末に豊かな実りを得るように、一つの家庭が福音によって実を結ぶには粘り強い祈りと涙の献身が求められるが、最終的には「涙を流して種を蒔く者が、喜びの束を刈り取る」という約束が成就するのである。
張ダビデ牧師は、具体的な宣教戦略を描きながら「アメリカの50の州にそれぞれ地域教会を建て、それらがさらに世界の貧しい国々に福音のセンターを建てていけば、100カ国、1000カ国への伝道も夢ではないのではないか」というビジョンを提示する。そして、このために必要な資源はどこから来るのかについて「サレプタのやもめ」の比喩を持ち出す。世の常識では十分に余裕があるときにしか分かち合えないが、福音的な観点では「最も不足しているときに捧げる献身」が神の前で豊かに満たされるカギとなる。こうした霊的原理に従って献身する人々が集まるとき、いわゆる「大いなる宣教運動」が少しずつ具体化され、拡大されていく可能性がある。
結局、宣教は「集団的・組織的な戦術」だけでなく、個人と家庭の小さな献身が集まって成し遂げられる総合的な働きである。誰でもどこでもネットに接続できる時代に移行しつつある今、教会はもはや教会堂の中に留まり続けることを固執してはいられない。絶えず世に出て行き、「涙を流して種を蒔く」働きをしなければならない。そして、そのように種を蒔く者たちに、詩篇126篇ははっきりした約束を与える。「必ず喜びの束を携えて帰ってくる」。
この約束を握ることが、張ダビデ牧師が詩篇126篇を通して強調する核心の一つである。救いの感激から始まった賛美、そしてその賛美が導く宣教的実践には、いつも尊い涙と献身がともなう。しかしその最後に待っているのは空っぽの手ではなく、豊かな霊的収穫の束である。言い換えれば、教会は涙と汗を流して種を蒔くという「使命」を与えられており、神はその献身を決して無視されないということだ。
だからこそ、私たちは覚えておくべきである。蒔かずして刈り取ろうとするのはただの幻想にすぎない。安易に伝道や宣教を行う道はなく、苦難と困難は必然的に伴う。しかし一度でも種を蒔いた者は、その過程で神が与えてくださる慰めと報いを体験することになるだろう。「泣きながら種を蒔きに出て行く者は、必ず喜びの束を携えて帰ってくる」という詩篇126篇のメッセージは、教会の頭であるイエス・キリストの地上の大命令とも一致する。「あなたがたは行って、すべての国の人々を弟子としなさい(マタイ28:19)」という命令の中には、すでに「涙を流して種を蒔く」献身を求める重みが込められている。
しかし、その道が決して絶望や落胆で終わらないことを、聖書ははっきりと約束する。むしろ「いのちを得た者たち」が再び他の人々にいのちの種を伝え、その人々がまた福音の伝達者となるという驚くべき「いのちの連鎖反応」が起こるからである。初代教会がそうであったように、一度燃え上がった福音は周囲の人々に連鎖して、また別の教会を生み出し、さらに別の宣教地を開拓していく。これこそ「喜びの束を刈り取る」姿の具体的実現だと、張ダビデ牧師は説いている。
詩篇126篇を通して私たちがはっきり見ることのできる大きなテーマは二つある。第一に、捕囚状態から解放されたイスラエルの民に訪れた「救いの感激」がいかに驚くべきもので、喜びに満ちていたかということ、そしてその喜びが自然に賛美へとつながるという事実である。第二に、その救いの喜びを体験した者たちが、「涙を流して種を蒔く」という姿勢で世に福音を蒔かなければならないという「宣教的使命」である。この二つは分離されず、相互に密接に連動している。救いの感激が真の賛美へとつながるとき、その賛美は再び宣教への情熱を呼び起こし、より多くの魂が福音に触れられるように教会を促す。
張ダビデ牧師は、詩篇126篇こそがまさにこの「救いの喜びと宣教の献身」を統合的に示す優れた本文だと語る。私たちがこの詩篇を読むたびに心に留めるべきなのは、イスラエルがバビロン捕囚から解放されたのは決して彼ら自身の力や知恵によるものではなかったという点だ。あくまでも神の摂理と、時が満ちて成し遂げられた御業であった。同様に、現代の教会が全世界に福音を伝え、虐げられている人々に解放のメッセージを伝えられるのも、ただ神の恵みと導きによるからである。その恵みをまず受けた者たちは、その感激を賛美として歌いつつ、同時に惜しみなく涙を流しながら種を蒔く現場へ出て行かなければならない。そしてその献身ののちには、いつの日か「喜びながら刈り取る」瞬間を迎えるだろう。
ゆえに、このみことばを今日の私たちの生活に適用するならば、教会の各聖徒は個人的にも、共同体としても宣教的ビジョンを抱き、種を蒔くべきである。それが個人伝道であれ、海外宣教であれ、地域奉仕であれ、あるいは家庭の福音化であれ、その形は異なっていても本質は同じだ。「涙の種蒔き」がなければ「喜びの収穫」もあり得ない。この原理は経済原理や組織管理方式では置き換えられない、聖書が示す霊的法則である。そしてこの法則を握る教会こそ、「地の果てまで福音を伝えよ」というイエス・キリストの命令に積極的に従う教会になるのだ。
詩篇126篇で詩篇記者が「私たちは夢を見ているようだった」と告白したのは、神の救いの御業が人間のあらゆる想像を超えていたからである。私たちも同じように、救いの驚くべき御業を体験するなら、その感激を禁じ得ない。そしてその感激は「神への賛美と宣教的献身」へと自然に導かれる。このすべての過程を通じて、張ダビデ牧師が強調するように、教会は集まることを大切にしつつも散らされ、散らされては再び集まって再充電と訓練を受けることで、さらに大きく神の救いの計画に参与するようになる。そうできるように、教会ごと、家庭ごと、そして個人の人生ごとに日々注がれる恵みを心から願い求める。
「主よ、ネゲブの流れのように私たちの捕われ人を帰らせてください」という嘆願は、現代においても有効な祈りである。人生のさまざまな捕囚状態にある人たちがいるなら、彼らも神の解放を求め、救いが訪れた後には賛美と宣教的献身へと進むべきである。その道が決して平坦ではなくとも、詩篇126篇が示す歴史は明らかだ。涙を流して種を蒔いた者たちは、時が満ちると必ず喜びの束を手にして帰ってくるということである。これこそ「救いの感激」と「宣教の使命」を共に握るすべての聖徒に与えられる祝福であり、この地上の教会が歩むべき道である。そしてまさにそのとき、教会は世の塩と光として真の役割を果たすことになるのだ。
張ダビデ牧師は、このようなメッセージを通して、教会がまぎれもなく「神の救いの御業」を行うために建てられた「宣教共同体」であることを改めて思い起こさせる。かつてイスラエルの民がバビロン捕囚から解放され、その感激を詩篇126篇で賛美したように、私たちもまた罪と死から解放されて賛美と喜びを回復するべきである。そしてその喜びの結実として、世界に福音の種を

















